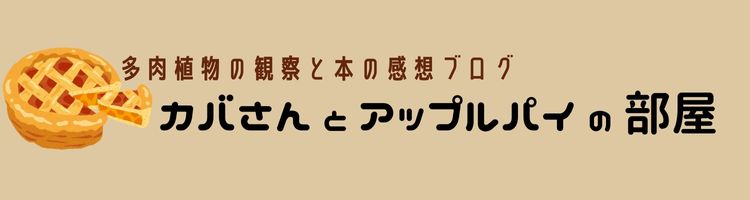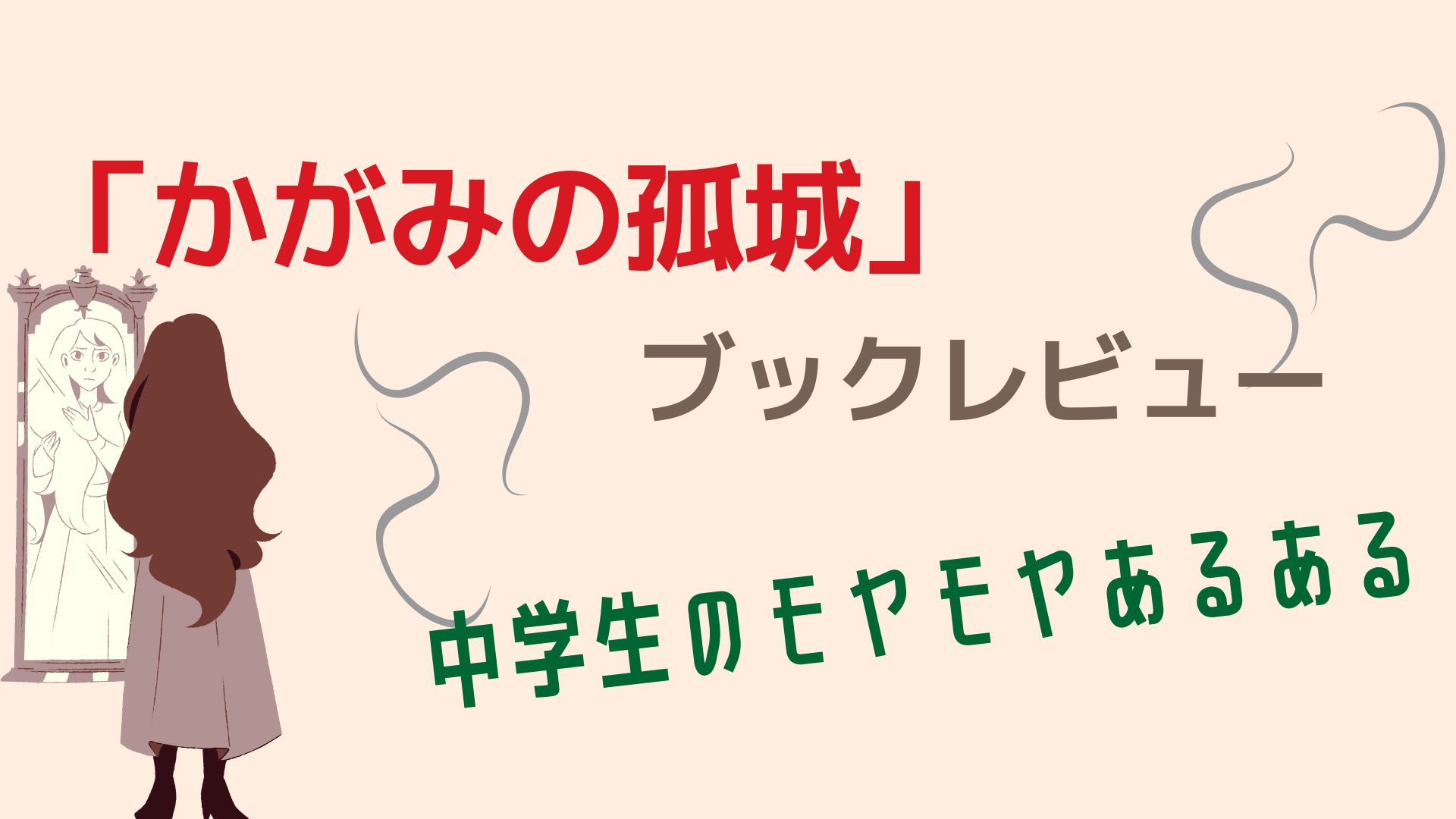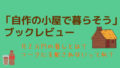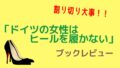久しぶりに長編小説を読みました。
年末ぐらいから読書欲が高まっていたので、ネットで【小説 おすすめ】とベタな検索で何度も紹介されていたので、気になって読んでみました。
辻村深月さん著『かがみの孤城』です。
ざっくりあらすじ
いろいろな理由で学校へ通っていない中学生7人のお話し
ある日、鏡の中の世界に入り込んだ7人
学校へ行かない理由は様々
7人がお互いに学校に行ってないと認識しつつも触れちゃいけない空気感からしばらくの間は自分のことを話さない日々が続きます
ところが、ぽつぽつと自分自身のことを話すようになり7人の共通点を発見します。
注意点
おそらく誰しもが経験していそうな中学生あるあるのモヤモヤ感を思い出すお話しでした。
別に不登校の人じゃなくても、中学生のときにあった微妙なバランス感。スクールカーストって言葉が生まれる前から、何となくグループ同士でのランク付けみたいなのがあって、お互いに自覚している。
みたいな。
女子だけじゃなく男子も、明確な”いじめ”じゃなくても小バカにされたり、クラスのリーダー格の思惑と違うことをしたら自分が外される・・・みたいな心がザラッとした気持ちをした体験を思い出してしまうお話でした。
なので、学生時代のイヤことがあった人、思い出したくない人にはつらいと思います。
こんな人におすすめ
この本をおすすめしたい人は、
子育て中の親とか、学校の先生とか、中学生と接する機会のある人たち。
主人公のこころ(中一)は、あることがきっかけで、クラスのリーダー格に目をつけられてしまい、学校に行けなくなってしまいました。
こころの両親はそのことについて、心配したり、戸惑ったりします。こころも両親が本当は学校に行ってほしいという気持ちがあるということをひしひしと感じながら、辛い思いを言えない。
言うタイミングを逃してしまった。
また、こころの担任の先生は、”仕事として”家庭訪問に来るが、こころに寄り添った対応とはいえず、それによってまた傷つけられていく。
寄り添うとか傾聴ってなんだろう
担任の先生は、リーダー格の子の話がすべてであるかのような認識で、こころに接する。それがこことにとっては衝撃で、話の通じない大人なんだと思う。
一方で、フリースクールの先生は、こころに『自分の話を聞いてくれるかも、話してみようかな』と思わせる何かを持った人。
大人の揉め事でもそうだけど、最初に片一方の話を聞いた時は、そっちの話が全てに感じてしまうことがある。そして、それは相手側がちょっと・・・と思ったりすることがある。
でも、いざ相手側の話を聞いてみると、全然話が違うなんてのはあるあるですよね。
同じ出来事を話していても、とらえ方、解釈の仕方、その時の気持ちが各々で違う。
悪気が無くても相手が傷ついていたり、良かれと思ってやったのに実は本人は嫌だったり・・・
大人になっても、職場内で発生したりもするけど、そういう人とは適度に距離を置いたり、嫌なことを受け流したりかわす方法を身につけて、自分を守るようになっていく。
でも中学生はまだそこまでの身のこなしができない年齢で、でも大人や学校の先生は『よくあること』として真摯に話を聞いてくれる人は少ないんじゃないかな。
少なくとも私は中学の時に信頼できる大人っていたかな?何か問題があっても、担任には相談しなかっただろうし、両親に本音を話すこともなかったんじゃないかな。
ただ、時が経つのをじっと待つというか、嫌なことに目をそらしながら、事なかれ主義な中学生だったような気がする。
幸い私の中学生時代には”いじめ”らいしいじめはなかったと思っているけど、でもいつもの4人グループのうちだれか一人をのけ者にするような期間があって、それが何となくローテーションしていて、『ああ、自分の番がきた』みたいなことがあったな。
たぶん他のグループも近いものがあって、さらにいつも仲良し2人組のうち片方に彼氏ができて、もう一人が別のグループに合併、その後彼氏と別れた時には合併したグループにも加入できずにボッチになってしまう・・とかも見てきた。
でも、そこで誰かが声をかけることもなく、他のグループも我関せずみたいな感じ。
それって今だといじめになるらしい。
私は一時期、教育委員会のいじめ・不登校・発達障害を担当する人たちとかかわったことがあって、現代のいじめの定義は、本人が嫌な気持ちになったら学校はいじめと認知すると聞いたことがある。
極端な話、好きな人に告白しました、断られました→嫌な思いをした
これを先生に話すといじめと認知するらしい。
一方で、告白されました、断りました、その後もなんやかんや付きまとわれたり噂されて嫌な思いをしました
これもいじめと認知するらしい。
ちなみにこの”認知”ってのは”いじめがあった”とは違うらしく、嫌な思いをした人がいる→じゃあお互いの話を聞いて確認しましょうの段階らしい。
だから、彼氏と別れた後にもともと仲良かった友達が他のグループに行ってしまった、友達がいなくなってしまった、クラスで話せる友達がいなくなってしまった、ボッチになってしまった、寂しいな、嫌だな
これを親に相談→学校へOR先生に話す=いじめの認知
らしい。
んで、ボッチに気が付いていた子は加害者なのか?
いじめって直接加害を加えた本人以外にも、見て見ぬふりをした人もいじめだよ。
って言われてるらしいけど、なんかクラス全員で仲良くしましょうってのも気の毒だなあとおもったりもした。
もちろん、明らかな仲間外れとかいやがらせとかだったら、別だけど、
クラスでボッチの人がいます。でも私はその子と何となくソリが合わないので特に仲良くしたいとか、毎日話したいとは思っていません。でもいやがらせは絶対にしません。
そんな、好きでも嫌いでもないけど特段関わらない人、通勤電車で毎朝同じ車両で見かける人でも、それがクラス内だったら仲良くしなきゃいけないのってなんか理不尽だったなあって思います。
それに、昔は殴る蹴るの取っ組み合いのけんか、いじめだったみたいですが、今はネット上で繰り広げられてるから、なおさら親とか年配の先生は理解できない。
だからなおさら中学生と大人の話がかみ合わなくなって、何から説明したらいいのかわからない、説明したところで理解してもらえないんじゃないか。そんな気持ちから誰にも話せず一人で抱え込んじゃうのかな。
私は昔、仕事で業務量の多さが辛くて、毎日時間に追われて、でも日中は電話対応ばっかりで進まなくて、毎日焦っていて辛くて
それを上司に相談したことがあった。
で、一通り話をした後帰ってきた言葉が『で、何がそんなにつらいの?』でした。
一応、仕事なので、業務量を件数や時間などの数字に落として話しましたよ?
別に感情論をぶつけたわけではなかったつもりです。
でも、『何が辛いの?』でした。
『・・・じゃあ日中の電話の1本でも取ってください』って言葉が喉元まで上がってくるのを感じながら、
ああ、この人には通じないんだ。とすべてをあきらめたことがあります。
主人公のこころも担任の先生に感じた絶望感は私の比じゃないんだろうと思うと、胸が締め付けられるようでした。
誰か一人でもその絶望感をくみ取って、共感してくれる人がいたら・・・
主人公は鏡の中で他人とのコミュニケーションの取り方を思い出しながら、フリースクールの先生との出会いもあって徐々に母親に打ち明け、味方になってもらい今後のことを一緒に考えるようになりました。
コロナをきっかけに不登校が増えたとニュースで見たことがあります。
主人公も当初、学校か、家かそれ以外に居場所がないと感じていて、学校に居場所がなくなると家しかない。でも学校に行かないと家でも居場所がなくなっていく。
でも、担任の先生が家庭訪問に来てフリースクールもあるよーって伝える時の言い方を誤ってしまうと、子供は問題児をフリースクールに押し付けたみたいにとらえられかねないから、難しいのかもしれない。
中学生にもなれば大人の顔色を伺うこともあれば、相手の本音を読もうとするし。
だから事務的に言われたのか、本当に自分のことを思って行っているのかが伝わっちゃう。
これは私の勝手な予想だけど、人の心の痛みって我慢して耐えてきた人ほど、『その程度の痛み』ととらえてしまう癖があるから、だんだん痛みに鈍感になっていくんじゃないかな。
そうしないと、自分が傷つきやすいままだから。
そんなことを感じた1冊でした。
読んだ後、数日間はこの本の話の影響で、いろいろと学校というものを考えてしまいました。
全員が中学生だった経験があるから、自分の経験に戻づいていろいろ言ってくる人が多いし、アドバイスしたがる人も多いけど、それが自分の話をしたいだけなのか、本当に相手の気持ちを考えた発言なのか、いろいろと思いを巡らせるきっかけになりました。
おしまい